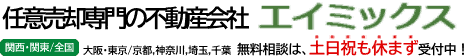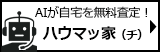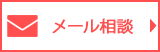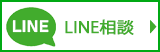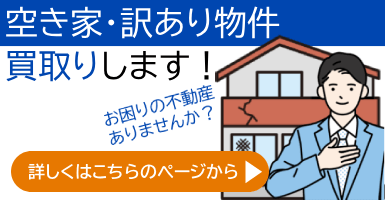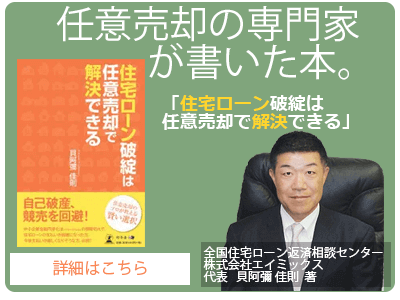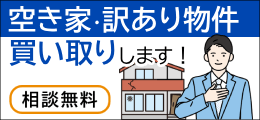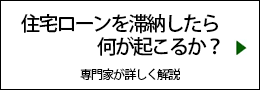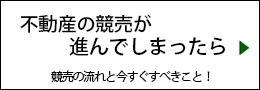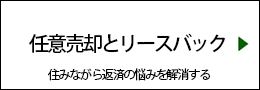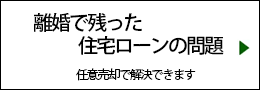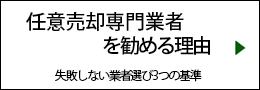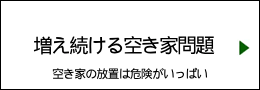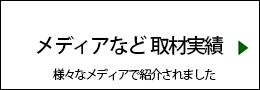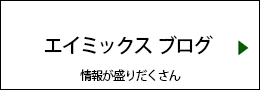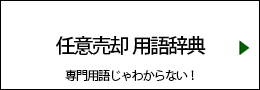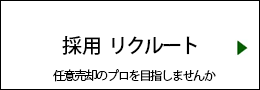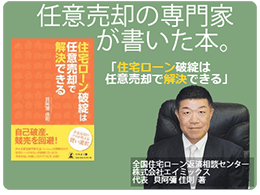相続した不動産を売却すると税金はいくら?最新の計算方法と使える特例を解説
 空き家問題
空き家問題
親や親族から相続した家や土地を売却するとき、「税金はいくらかかるのか?」は誰もが気になるところです。この記事では譲渡所得の計算方法、税率、よくある落とし穴、そして活用できる特例を最新の制度に基づいて整理します。専門用語を抑えつつ、実務の流れに沿ってわかりやすく説明します。

監修
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
宅地建物取引士/公認不動産コンサルティングマスター/
2級ファイナンシャルプランニング技能士/賃貸不動産経営管理士/相続診断士
大手不動産仲介会社の法人営業部で任意売却部門を立ち上げ、
銀行・保証会社・破産管財人弁護士などと連携し、住宅ローン返済に困難を抱える方々の相談を300件以上担当。
相続した不動産を売ると税金はかかる?
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)がかかります。売却価格が取得費や譲渡費用を下回る場合は課税されません。まずは「利益が出ているか」を確認することが第一歩です。
不動産売却でかかる税金の計算方法
基本的な計算式は次のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)各項目の確認ポイント
- 取得費:被相続人がその不動産を購入した際の金額や取得にかかった費用。資料がない場合は概算取得費(売却価格の5%)を用いることが認められています。
- 譲渡費用:仲介手数料、測量費、登記費用、立退料など、売却に直接関わる費用が該当します。
- 所有期間:相続の場合は、被相続人がその不動産を取得した日から起算します。相続後すぐに売却しても、長期譲渡扱いになる場合があります。
税率の目安(所得税・住民税・復興特別所得税を含む)
| 所有期間 | 区分 | 税率(合計) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 約39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 約20.315% |
相続不動産で起きやすいトラブル
売却前に次の点を確認しておくことで、余計な税負担や相続トラブルを避けられます。
- 相続登記を完了し、名義人が自分になっているか。
- 被相続人の購入時の契約書や領収書など、取得費を証明できる書類を保管しているか。
- 共有名義になっている場合、全員の同意が取れているか。
取得費が不明のまま申告すると、税務署により概算(売却価格の5%)で計算され、結果的に課税額が高くなることがあります。
使える主な特例・控除(2025年時点)
条件を満たせば、譲渡所得を減らせる特例や控除を利用できます。申告前に要件の確認が必要です。
- 被相続人居住用財産の3,000万円特別控除(空き家特例) 被相続人が住んでいた家や敷地を、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、最大3,000万円を控除。令和9年12月31日まで延長。
【令和6年以降の譲渡に関する重要な改正】
1)相続人が3人以上いる場合、控除額の上限は2,000万円に減額されます。
2)買主が譲渡後に家屋の耐震改修または取壊しを行った場合も適用対象となりました。 - 相続税の取得費加算の特例 相続税を納めた場合、その一部を取得費に加算できる制度。その財産を相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡する必要があります。
※どの特例も要件が細かく、申告方法を誤ると控除が受けられません。不安がある場合は税理士など専門家に相談しましょう。
確定申告と納税の流れ
不動産を売却した場合、翌年に確定申告を行い納税します。通常の確定申告期間は翌年の2月16日から3月15日で、年度や暦日によって多少前後します。最新のスケジュールは国税庁ホームページで確認するのが確実です。
申告漏れや特例の申請忘れがある場合は、更正の請求や修正申告の手続きが必要になるため早めの確認が大切です。
実務上のおすすめ手順
- 被相続人の契約書・領収書など取得費を確認できる資料を集める。
- 相続登記と共有関係を整理し、売却準備を整える。
- 該当する特例があるかを税理士に確認し、控除の取りこぼしを防ぐ。
この記事のまとめ
相続した不動産の売却で課税されるかどうかは「譲渡所得が出るか」がポイントです。
取得費の確認、相続登記、適用できる特例の確認を行い、必要に応じて税理士など専門家に相談することが大切です。
※本記事は2025年11月時点の法令等に基づいた一般的な解説です。
個別の税務判断・申告内容については、必ず税理士などの専門家にご相談ください。